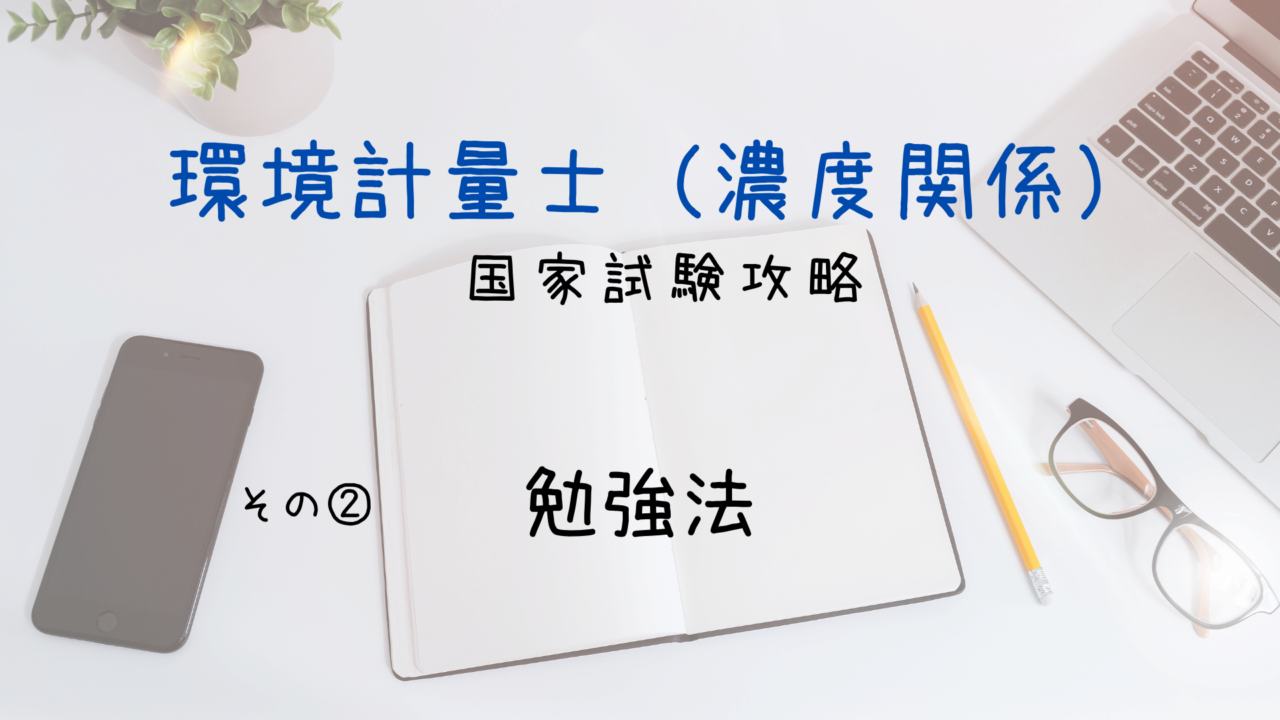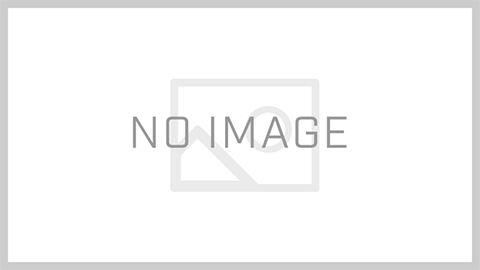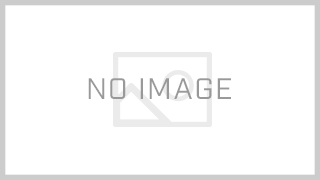こんにちは!
Thinkです(Twitterアカウント👉https://twitter.com/Think_blog_2019)
今回「環境計量士の試験を受験したい(した)けど、何を勉強すればいいのかわからない」といった方のために、どのような情報を元に勉強したらいいか解説する記事を書きました。
環境計量士の試験に初めてチャレンジする方のためにも全般的なことを書いています。
①どのような参考書を買えばいいか?
参考書といっても沢山あります。
ではどのような参考書を買えばいいのでしょうか?
私が実際に受験してみて、必要だと思った参考書は以下の3つです。
✅過去の問題とその解き方が掲載されている参考書
✅化学について記載されている参考書
✅分析機器について記載されている参考書
過去の問題について
実は過去の問題と正解の番号が経済産業省のホームページに掲載されています。
ただ、解き方は掲載されていないので、試験勉強に使うには物足りないです。
解き方まで知りたい方は、この参考書をオススメします。
👇環境計量士(濃度・共通)攻略問題集
この参考書は過去7回分の試験の解き方をすべて掲載しています。
そして、環境計量士の濃度関係については毎年直近の試験まで掲載した物が発売されますので、常に最新の情報を入手することができます。
最新版は4月あたりに発売されますので、購入は4月まで待ったほうが良いです。
化学の参考書について
化学については、大学レベルの化学知識が必要ですが、大学受験(=高校化学)の知識でも、応用が前提ですが充分解くことができます。
そのため、高校化学+αの内容が記載されている参考書が良いです。
私のオススメは以下の商品です。
👇理解しやすい化学 化学基礎収録版
この参考書は高校化学はもとより、大学の化学にも触れていますので、基礎固めをする上でちょうどよい参考書です。
実際の環境計量士の試験では、この参考書よりもレベルが高い問題が出題されますが、基礎を固めていれば解けてしまう問題もあります。
化学の勉強で悩んでいる方はぜひ購入してみてください。
どうしても化学が苦手で、どうやって勉強したらいいかわからない・・・・
という方のために、化学の勉強方法についてnote記事を書きましたので、こちらも是非ご活用ください。
分析機器の参考書について
分析機器については、実際に扱った事がある方であれば勉強する必要がないと思いますが、扱った事がない方は未知の領域といっても過言ではないと思います。
また、環境計量士の試験では上記の化学の参考書でも書いた通り、レベルが高い問題が出題されます。
そのため、分析に必要な化学知識と分析機器の両方について書いてある参考書が良いです。
私のオススメは以下の参考書です。
👇基礎教育 分析化学
この参考書は環境計量士で必要な化学知識 と分析機器の両方について書いてある本です。
本のタイトルに「基礎教育」と書いてありますが、結構難しい内容です。
ですが、「化学の参考書」で紹介した参考書と一緒に勉強すれば、理解できる内容です。
環境計量士の合格ラインまで分析化学の知識を上げたい方は、是非検討してみてください。
②法令の参考書について
次に法令の参考書についてですが、法令については参考書をあまり利用しないほうがいいです。
その理由は
✅最新の法令を勉強する必要があること
✅過去問を勉強するだけで十分
だからです。
「じゃあ法令はどうやって勉強すればいいの?」と思う方もいらっしゃると思います。
というのも参考書のほとんどが、発売されてから数年経過していて、常に最新の情報が掲載されているものは少ないです。
そのため、法令が改正されていても対応できていないです。
過去1年以内に発売された参考書であれば良いですが、それより昔に発売された参考書は、上記理由から購入しない方が良いでしょう。
ただ、法令の問題は毎年似たような問題が出題されるため、過去問の参考書は勉強に使えます。
過去問の参考書で勉強しても、改正された法令に対応することはできませんが、最低限合格点は狙えます。
③最新の法令はどこで見ればよいか?
最新の法令は電子政府の総合窓口及び経済産業省のホームページで公開されています。
過去問の参考書を使うことで出題される場所が大体わかりますので、その部分に関する最新の情報を勉強しましょう。
以下に各法令のリンクを掲載します。
④JISはどうやって勉強すればいいか?
JISは書籍で販売されていますが、すべて入手しようとすると高額になります。
また、JISもたまに変更されていますので、法令と同じように最新の情報を勉強したほうが良いです。
過去問から出題されるJIS番号を把握し、その最新の記載内容を勉強しましょう。
JISについてはこちらのサイトで閲覧することができます(印刷不可)
⑤参考書以外の勉強方法は?
環境計量士の国家試験対策セミナーというものが毎年開催されています。
その中では、講師の方が前回のテストが行われてから変更があった法令や、過去の出題傾向をまとめた資料を配布してくれます。
法令やJISに関して短時間でまとまった情報を入手したい方はぜひ受講してみてください。
一般社団法人 日本環境測定分析協会で開催しておりますので、気になる方はこちらのリンクをご参照ください。
新型コロナウィルスの影響で、オンライン開催になっているようです。
ただ、注意してもらいたいことがあります。
それは「このセミナーを受講しても国家試験が免除になるわけではない」ということです。
他の資格では、セミナーを受講することで試験が免除になるものもあります。
しかし環境計量士はそのようなことはなく、国家試験に合格するか、定められたカリキュラムを修了する必要があります。
この講習会は、あくまでも試験対策のセミナーです。
⑥まとめ
今回は環境計量士をこれから受験する方のために、試験勉強に必要な情報をまとめてみました。
化学について、「化学に関する雑学力」が必要となる問題がでますので、参考書のコラムも一緒に読んでおく事をオススメします。
法令やJISについて、最近は国際キログラム原器廃止といった大きな変更が発生していますので、法令やJISについては、常に最新の情報を把握するようにしてください。
⑦分析機器の原理について
①の項で紹介した参考書や過去問を勉強することが一番です。
また、私のサイトでも分析機器の原理についてざっくり解説した記事を掲載しておりますので、こちらもご参照ください。
⑧問題の解き方テクニックについて
過去問を使用して、問題の解き方、考え方も記事にしています。
是非ご覧ください。
【初心者向け】環境計量士(濃度関係) 国家試験攻略 その③ ~問題の解き方 環化編~
【初心者向け】環境計量士(濃度関係) 国家試験攻略 その④ ~問題の解き方 環濃編~
・【初心者向け】環境計量士(濃度関係)の解き方 第71回環化編
⑨参考書を電子化する方法
環境計量士に限った話ではないのですが、参考書を複数冊所持していると、持ち運びが大変ですし、保管に場所も取ります。
参考書を電子化してiPadを活用することで、重い書籍を持ち運ばなくて済むようになりますし、ノートも参考書もすべてiPadに一本化できます。
参考書の電子化についても記事を書いておりますので、参考書の持ち運びが大変だったり、保管場所がないという方はぜひご覧いただければと思います。