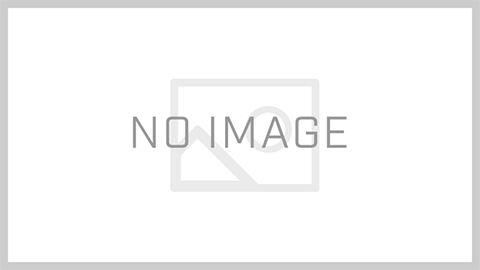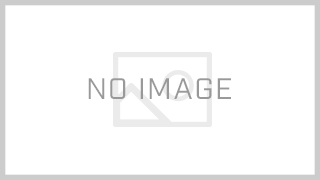①第六類って何?
危険物の第六類は、「酸化性液体」です。 概要は 「他の可燃物の燃焼を促進する液体」 です。 どこかで見たことありますね。 そうです、第一類と似たような性質です。 酸化性液体
- 酸化する
- 性質を持った
- 液体
②第六類に指定されている物質
第六類は、化合物毎に分類されています。 第六類は、他の類と比較してそこまで数は多くないですし、複雑な構造もありません。 また、指定数量は全部一緒で、「300kg」です。 第六類共通の特徴ですが
- 分子内に過剰な酸素が結合している
- ハロゲンとハロゲンの化合物
<過塩素酸>
第一類では過塩素酸ナトリウムがありましたが、こちらはナトリウムの代わりに水素が結合しているものです。 不安定な物質で、とても酸化力が強いです。 そのため、可燃物と混ぜるだけでなく、ただ貯蔵していても徐々に分解し、爆発する危険性があります。 もちろん、可燃物と混ぜるのもダメです。<過酸化水素>
水分子にさらに1つ酸素が結合した物です。 こちらは、ケガをしたときに使う消毒液のオキシドールの主成分です。 消毒に使うのは、3%程度の水溶液ですが、工場や実験で使う時はもっと濃い物を使います。 しかし、濃度が50%以上になると、急速に分解する可能性が高くなり、爆発することもあります。 もちろん、可燃物と混合するのはダメです。 消毒液のような濃度が低いものであれば大丈夫ですが、濃度が濃い物に可燃物と接触すると、急激に酸化が起こり、爆発します。<硝酸、発煙硝酸>
硝酸は水に二酸化窒素が溶解したものですが、86%以上溶かしたものを発煙硝酸といいます。 なぜ発煙するのかというと、二酸化窒素の水に溶ける限界量付近の濃度なので、水から二酸化窒素が揮発してくるためです。 いわゆる満員電車のようなもので、ドアが開いた瞬間に人が流れ出てしまう(=二酸化窒素が空中に飛び出す)ようなものです。<その他政令で定めるもの>
具体的には です。 これらは、臭素やよう素といったハロゲンに、ふっ素が結合した物です。 不安定な物質で、水や可燃物と接触すると激しく反応し、発熱します。 また、猛毒のふっ化水素を発生しますので、火災時には水系の消火剤は使えません。<試験>
・燃焼試験 酸化力の潜在的な危険性を評価する試験
④第六類全体の共通事項
<特性>
- 不燃性の液体
- 無機化合物
- 酸化力が強い
- 腐食性があり、蒸気が有毒
<火災予防方法>
<消化方法>
- 水や泡消火剤(ハロゲン化物はダメ)
- 二酸化炭素やハロゲン化物を用いた窒息消火は効果が無い
⑤まとめ
第六類は酸素を出して可燃物を酸化させる「酸化性液体」です。 自身が酸素をだしますが、第五類と異なり、自身は燃えないです。 酸化性なので、他の危険物を運搬するときは、同一車両に以下の物と一緒に積んではいけません。
- 第二類(可燃性固体)
- 第三類(自然発火性物質、禁水性物質)
- 第四類(引火性液体)
- 第五類(自己反応性物質)