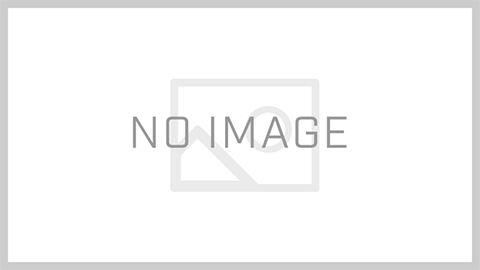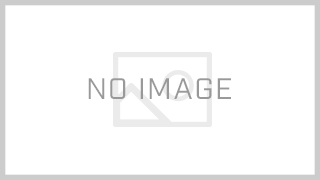こんにちは!
Thinkです(Xアカウント👉
https://x.com/Think_blog_2019)
今回は危険物取扱者の試験を初めて受験する方のために、第五類の特徴について記事を書きました。
乙第五類を受験する方だけでなく、甲種を受験する方でも参考になるかと思いますので、今後受験しようと考えている方やまさに受験勉強をしている方は、是非ご覧いただければと思います。
👇
危険物取扱者の概要は以下の記事で解説しておりますので、こちらも併せてご覧ください。
www.think-diary.com
①第五類って何?
危険物の第五類は、「自己反応性物質」です。
概要は
「熱分解などで自己反応を起こし、比較的低い温度でも沢山熱を発生したり、爆発的に反応が進行する固体または液体」
です。
ちょっと長文ですね。
まずは文字の意味から考えていきましょう。
引火性液体
- 自己反応を起こす
- 性質を持った
- 固体または液体
です。
気体は含まれないのでご注意ください。
「自己反応」について説明します。
他の危険物では、「引火」「発火」「酸化」といった表現が使われます。
酸化はともかく、引火や発火については、なんとなく「火が付きやすいんだな」といったイメージを持てるかと思います。
ただ、第五類の「自己反応」については、いまいちイメージしにくいですよね?
自己反応というのは、「自分で反応する」ということです。
これだけだと、ちょっと何を言っているかわからないと思います。
自分で反応するというのがどのようなことか説明します。
例えば物が燃えることについて考えてみると、燃やすものと燃えるものが混ざって、反応して、燃焼します。
酸素と水素が混じった状態で反応が起これば、燃えます。
自己反応性物質は、燃やすものと燃えるものがあらかじめ混じっている物です。
しかも、それぞれ別の物が混じっているのではなくて、「分子の中に燃やす部分と燃える部分」を持っているのです。
なので、「周囲に酸素が無くても、自分で酸素を出して自分が燃えます。」
これが自己反応性物質の基本的な性質です。
概要の部分にも書きましたが、熱分解で自己反応が始まります。
熱以外にも、摩擦、衝撃なと、いわゆる刺激を加えることで、自己反応が始まり、反応が進むことによって、酸化が起こりますので、更に熱が発生します。
このサイクルが加速して、最終的に激しい燃焼や爆発が発生します。
なので、第五類には爆薬として使われている物質もあります。

②第五類に指定されている物質
第五類は、化合物毎に分類されています。
- 有機過酸化物
- 硝酸エステル類
- ニトロ化合物
- ニトロソ化合物
- アゾ化合物
- ジアゾ化合物
- ヒドラジンの誘導体
- ヒドロキシルアミン
- ヒドロキシルアミン塩類
- その他の物で政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
とても細かく分類されていますが、第五類に共通する特徴として
- 分子内に窒素と酸素、あるいは両方を持っているものがほとんど
です。
まずは、危険物がなぜ危険なのかを考えてみましょう(哲学ではありません)。
我々が生きているこの世界では、「現象は安定な方向」に進みます。
危険物は、その化合物自体がとても不安定で、安定な形に変わるために反応しています。
第五類の場合、分子内に窒素と酸素が付いているものがほとんどですが、「化合物内の窒素が安定な窒素ガスに変化するために」酸素が発生して燃焼します。
これが第五類のキモになります。
例えば、爆薬として有名な
ニトログリセリンですが危険物の第五類に指定されています。
ニトログリセリンは衝撃を与えただけで爆発しますが、これはニトロ基の窒素が、より安定な窒素ガスに変わるために酸素を放出して、その酸素が爆発を引き起こします。
そのため、分子内に酸素と窒素を持っている物質、特にニトロ基のような、窒素と酸素が結合している物質は、危険物の可能性が高いということを念頭に置いていたほうが良いです。
<有機過酸化物>
具体的には
- 過酸化ベンゾイル
- エチルメチルケトンパーオキサイド
です。
過酸化というのは、分子内に酸素と酸素の結合があるものです。
この結合がとても不安定で、すぐに切れて他のものを酸化する(=燃える)ので、危険物に該当してます。
この2つの化合物名ですが、「過酸化」「パーオキサイド」が、酸素同士の結合を有している意味になりますので、これを抑えて置けば、理解しやすいのではないかと思います。
<硝酸エステル類>
具体的には
です。
硝酸の水素原子が、アルキル基に置き換わったものです。
この硝酸
エステル類と、ニトロ化合物はとても似ているので、違いを覚えていたほうが良いです。
まずは、「
エステル」について覚えましょう。
エステルというのは、アルコールと酸が反応してできた物質です。
おそらく一番有名なのは、酢酸エチルでしょうか。
酢酸エチルは、酢酸(酸)と
エタノール(アルコール)が反応してできた物質です。
硝酸
エステルは、この酢酸の部分が硝酸に変わります。
つまり、硝酸(酸)とアルコールが反応してできた物質が硝酸
エステルです。
具体的には、反応時に硝酸のHとアルコールのOHが水として抜けて、アルコールと硝酸が結合した物です。
硝酸メチル場合は、硝酸と
メタノールが反応してできた硝酸
エステルです。
では
ニトログリセリンとニトロ
セルロースはなんでしょうか?
ニトログリセリンは硝酸と
グリセリンが反応してできた硝酸
エステルです。
ニトロ
セルロースは硝酸と
セルロースが反応してできた硝酸
エステルです。
ここで重要なのが、
ニトログリセリンもニトロ
セルロースも「ニトロ」と名前がつきますが、危険物としてはニトロ化合物ではありません。
硝酸
エステルは、硝酸とアルコールが結合したもの
ニトロ化合物は、ニトロ基が炭素と直接結合したもの
この違いをよく覚えてください。
もし、試験で迷ったときは、
ニトログリセリンは何からできているのかを考えてもえればよいかと思います。

<ニトロ化合物>
具体的には
が該当します。
ニトロ化合物は分子内にニトロ基を持つ化合物になります。
ピクリン酸は、トリニトロフェノールです。
これは、フェノールにニトロ基が3個結合した物になります。
3個(トリ)のニトロ基(ニトロ)が結合したフェノールで、トリニトロフェノールです。
トリ
ニトロトルエンも同様に、
トルエンにニトロ基が3個結合した物になります。
3個(トリ)のニトロ基(ニトロ)が結合した
トルエンで、トリ
ニトロトルエンです。
<ニトロソ化合物>
具体的には
です。
ニトロソ化合物は、分子内にニトロソ基を持つ化合物になります。
この化合物は立体的な構造を持つ複雑な化合物なので、構造は覚えなくてもいいです
<アゾ化合物、ジアゾ化合物>
具体的には
- アゾビスイソブチロニトリル
- ジアゾジニトロフェノール
です。
分子内にアゾ基やジアゾ基を持つ化合物です。
それぞれの構造を覚える必要はないと思います。
具体的には
です。
ヒドラジンは2つの
アンモニアが窒素同士で結合しているような構造を持っています。
ロケットの燃料にも使われています。
ヒドラジン関係で有名なのは、猛毒キノコのシャグマアミガサタケをゆでると発生するモノメチル
ヒドラジンでしょうか。
シャグマアミガサタケ自体も有毒ですが、このゆでた時に発生するモノメチル
ヒドラジンも有毒です。
<ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン塩類>
具体的には
です
ヒドロキシルアミンと書くと、難しいようにきこえますが、基本骨格は
アンモニアです。
アンモニアの水素1つがヒドロキシル基に変わったのが、ヒドロキシルアミンです。
硫酸ヒドロキシルアミンは、硫酸とヒドロキシルアミンでできた塩です。
<指定数量>
- 第一種自己反応性物質:10kg
- 第二種自己反応性物質:100kg
<試験>
・圧力容器試験
加熱分解の激しさを評価
・熱分析試験
爆発の危険性を評価
④第五類全体の共通事項
<特性>
- すべて可燃性の固体または液体
- ほとんどのものが化合物内に窒素あるいは酸素を含んでいる
- 燃焼速度が非常に速い
- 火元だけでなく、熱、衝撃、摩擦でも発火、爆発する可能性がある
- 金属と反応するものもある
- 比重は1よりも大きい
- 非水溶性の物が多い
<火災予防方法>
- 火元、加熱、衝撃、摩擦を避ける
- 換気の良い冷暗所に貯蔵する(光でも反応する可能性あり)
- 乾燥すると爆発するものは湿潤させる
- 水があると危険な物は乾燥させる
<消化方法>
- 一つの化合物内に燃えるものと燃やすものが共存しているため、消火は困難
- 大量の注水で冷却するか、泡消火剤を使う
- 燃焼せず、いきなり爆発するので消火できないものもある
⑤まとめ
第五類は自分で酸素を出して自分が燃える、自己反応性物質です。
自信が酸素を出す他に、可燃物でもあります。
可燃物なので、他の危険物を運搬するときは、同一車両に以下の物と一緒に積んではいけません。
- 第一類(酸化性固体)
- 第三類(自然発火性物質、禁水性物質)
- 第六類(酸化性液体)
第一類及び第六類は酸化性の物質ですので、可燃物である第五類と
接触する可能性を無くさなければなりません。
また、第三類は金属なので、第五類と反応しやすいため、
接触を避ける必要があります。
逆に可燃性の物は他の物を酸化する力はあまり強くないので、一緒に積んでも大丈夫で