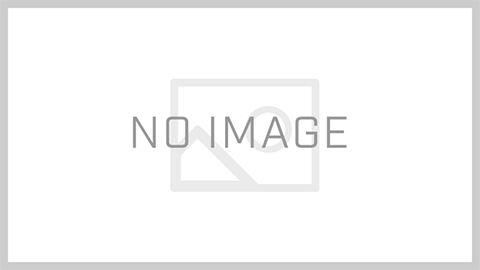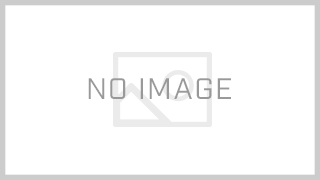こんにちは!
Thinkです(Twitterアカウント👉https://twitter.com/Think_blog_2019)
先日、Appleから、iPad用のOS「iPadOS」が発表されました。
これまでのiPadの用途のほとんどは、iPhoneの延長線上にありました。
しかし、今回のiPadOSにより、iPad独自の機能が追加され、より単体で扱いやすく、そしてPCの周辺機器が使えるようになりました。
今日は、追加された機能の中で、個人的に特に面白いと思った部分を紹介していきたいと思います。
公式のサイトのリンク
① 主な特徴と機能の向上(抜粋)
新機能の内容の中で一番気になったのは、「ファイル」機能です。
ファイル機能について、公式サイトより抜粋しました。
| ① |
カラム表示 |
新しいカラム表示では、フォルダの深い階層の中にあるファイルを簡単に探せます。ファイルを選択するだけで、高解像度のプレビューが表示されます。 |
| ② |
クイックアクション |
クイックアクションを使えば、PDFの回転、マークアップ、作成をファイルアプリの中で簡単に行えます。 |
| ③ |
豊富なメタデータ |
カラム表示では、豊富な一連のメタデータが示されるので、ファイルを探しながらそれぞれの詳細を見ることができます。 |
| ④ |
ダウンロードフォルダ |
新しいダウンロードフォルダでは、あなたがSafariからダウンロードしたファイルやメールアプリの添付ファイルにまとめてアクセスできます。 |
| ⑤ |
外付けドライブに対応 |
USBドライブ、SDカード、ハードドライブ上のファイルにアクセスできます。 |
| ⑥ |
iCloud Driveでのフォルダ共有 |
iCloud Driveで友だち、家族、同僚とフォルダを共有できます。相手がファイルを追加できるようにアクセスを許可することもできます*。 |
| ⑦ |
ローカルストレージ |
ローカルドライブに新しいフォルダを作って、よく使うファイルを加えられます。 |
| ⑧ |
ZIP形式の圧縮と解凍 |
ファイルを選んでZIP形式で圧縮すると、Eメールで共有するのが簡単になります。ZIPファイルをタップしてフォルダに展開すると、ファイルにアクセスできます。 |
| ⑨ |
ファイルサーバ |
SMBを使って、ファイルアプリから職場のファイルサーバや自宅のコンピュータに接続できます。 |
| ⑩ |
キーボードショートカット |
様々な新しいキーボードショートカットにより、ファイルアプリの操作がこれまで以上に簡単になりました。 |
| ⑪ |
検索候補 |
検索候補を利用すれば、あなたが探しているものが簡単に見つかります。候補をタップするだけで、すばやく検索結果を得られます。 |
| ⑫ |
書類スキャナ |
物理的な書類のデジタルコピーを作って、保存したい場所に直接置くことができます。 |
簡潔にまとめますと、ファイルの管理が、WindowsPCに近いことができるようになったようです。
実際にiPadで使ったわけではないので、どのような作業ができるかは所有者さんの動画レビュー等を見る必要がありますが、特に気になってる部分を赤く示しました。
②なぜ「ファイル」機能なのか?
過去の記事でも書きましたが、iOSの残念なポイントの1つとして、端末単体でファイル管理がほとんどできないことです(一応ファイル管理ができるサードパーティ製のアプリはありました)。
それが今回のiPadOSで可能となりました。
もちろん、完全にファイル管理をするのであれば、Windowsがベストですが、過去記事にも書いた通り、数あるタブレットの中で勉強に使用するのであれば、iPad+ペンシルの組み合わせが最強です。
そのため、ファイル管理がiPad単体で行えるのであれば、それに越したことはありません。
そして⑤の「外付けドライブに対応」とありますが、ここが最も気になっている部分です。
私個人の話にはなりますが、サムスン製のポータブルSSDを所有しているため、iPad ProであればUSB Type-Cケーブルを使用して直接つなぎ、必要なデータを直接移動することができると思います。
これまでは、一度PCもしくはクラウドを経由する必要があったため、大きな変化です。
↓所有しているポータブルSSDです。名刺サイズのコンパクトボディに、パスワード設定による暗号化も可能なので、重宝しています。
③注意点:直接USBを接続できるのは、第3世代iPad Proのみ
現在販売されているiPad Proは、接続端子にUSB Type-Cを使用しているため上記のようなポータブルSSDを直接つなぐことができます。
しかしほかのiPadは、まだライトニング端子を使用しているため、変換アダプタを経由して接続する必要があります。
iPadOSはiPad Air2以降のiPadに適用できるようですが、第3世代iPad Pro以外は注意が必要です。
④そして….
このファイル機能を確認するために、今更ながらiPad Pro第3世代を注文してしまいました。(第4世代iPad Proの噂もあるのに・・・)
物が届いたら、実際にどのような使い方ができるか記事を書きたいと思います。